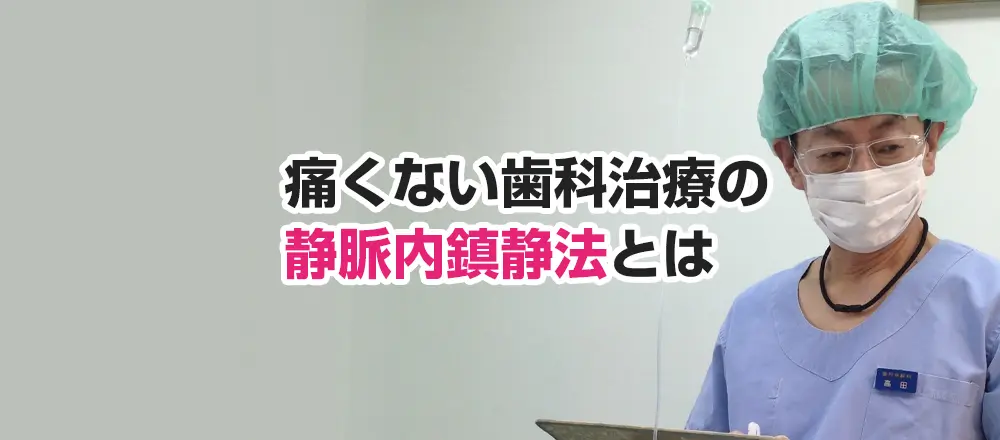
痛くない歯科医療と麻酔との関わり合い。「笑気麻酔」とは何?

痛くない歯科医療 黎明期の笑気麻酔とはどのような麻酔?
歯科医療と麻酔との関わり合いは深く、古くから歯の痛みは耐え難いものとされてきました。
殊に抜歯の時の何とか克服しよう歯科医師は幾多の努力を重ねてきました。
このことは麻酔の歴史における黎明期に、アメリカの歯科医師H.WellsやW.T.G.Moritonたちが活躍していることからもわかります。
我が国でも明治の中頃から早くも笑気麻酔が紹介され、歯科医療に使用されていました。
しかし、笑気は純笑気のみで使用したため、笑いながらばたばた意識消失し、死亡した症例もあった推測されます。
因みに英語では、Laughing gasと表記されます。現在では、笑気吸入鎮静法(I S)と呼ばれ、笑気と酸素を混合し、笑気濃度30%酸素濃度70%を鼻マスクから、吸入し、鎮静をおこないます。
痛くない歯科医療 黎明期の笑気麻酔のデメリットとは何か?
しかし、それなりの鎮静効果、例えば、手のひらの発汗や痺れ感、笑いなどの症状が鎮静効果のサインです。ただ、歯科治療中は口が開口し、口呼吸がおこりますから、笑気濃度は下がり、鎮静効果が、減弱してしまいます。また、現在では、環境問題から、笑気の空気中での半減期が60年とも、言われており、環境破壊の点からも、あまり推奨できなくました。
痛くない歯科医療と麻酔との関わり合い。「静脈内鎮静法(I V S)」とは何?
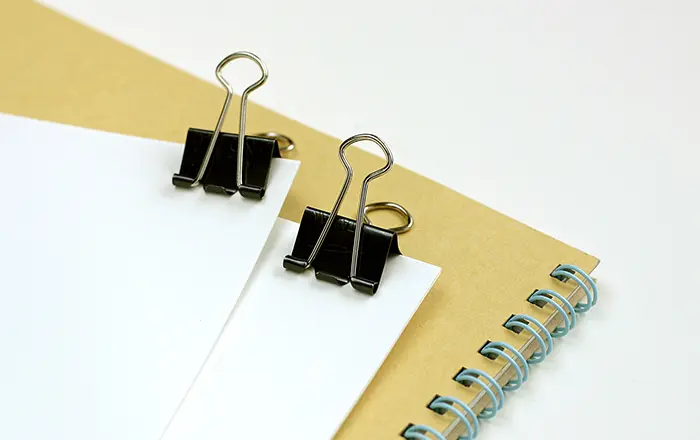
痛くない歯科医療としての静脈内鎮静法のはじまりは?
一方で精神鎮静法の中には、静脈内鎮静法(I V S)があります。昭和40年頃から、日本で東京医科歯科大学歯学部歯科麻酔学教室の初代教授であった久保田康耶先生がダブルライセンス(医師、歯科医師免許)の先生でしたので、直接血管、静脈に鎮静薬を投与法を考案され、実際施行したところ、これは、歯科治療に適応できるのではないかと始めた事を直接、久保田先生から、聞きました。
私はこの久保田教授の最後の愛弟子です。話を戻しますが、最初に使用された、鎮静薬はジアゼパム(セルシン)でした。
この薬は効果持続時間が長く、また脂溶性であるため希釈することができないため、投与法が非常に困難で、呼吸も停止してしまうこともあります。それ以降、ケタミン、フルニトラゼパムなどが発売されましたが、悪夢をみることがある、唾液量が増えることなどの副作用があり、静脈脈内鎮静は難しいと思っていました。 また、点滴確保もさまざまな血管がありますので、これを習得するのも大変です。
痛くない歯科医療としての静脈内鎮静法の進化は?
今から25年前に静脈内鎮静法の為のミダゾラム(ドルミカム)が発売されました。まさに静脈内鎮静法の為に開発された薬です。
この鎮静薬の特徴は、まず水溶性で希釈ができるので、何倍にでも希釈できるのです。静脈内鎮静法は患者の意識を消失させることなく、歯科治療中も患者とコミニケーションをとりながら出来ることこそが重要です。
医科では例えば、胃カメラで検査するとき、知らない間に終わったとか経験があると思いますが、医科のそれは、静脈麻酔(I V)と言って全身麻酔の一つなのです。したがって、医科には、静脈内鎮静法の概念は無いと思います。I V SとI VこのSとはSedation鎮静との意味です。
まとめ
最後に、歯科における静脈内鎮静法は、歯科治療に恐怖心がある方や高血圧症・糖尿病といった基礎疾患を有する方が治療中の循環動態の変動を少なくするなど、さまざまな利点があります。鎮静中は生体監視モニタ(血圧・心拍数・パルスオキシメーター・心電図)装置し、行いますので、是非とも一度経験してみてください。

ハーツデンタルクリニック西白井駅前の院長。城西歯科大学(現 明海大学)卒業。仕事でうれしい時は思うような治療ができ、患者様に喜ばれ、お礼を言われたとき。
ハーツデンタルクリニック西白井駅前



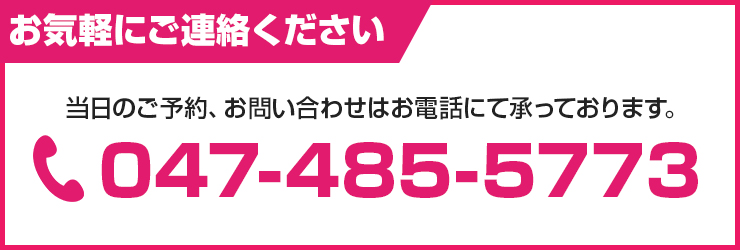

コメント