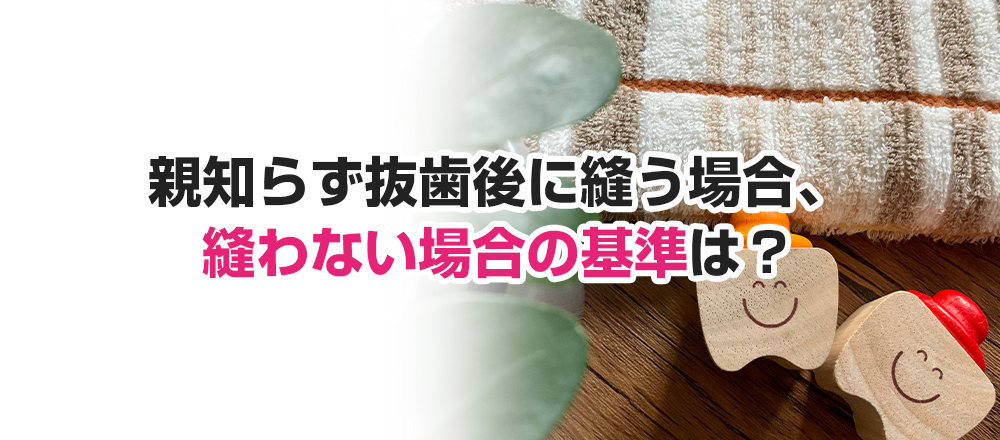
親知らずは、まっすぐ生えることが少なく、他の歯と比べて、抜歯が難しいケースが多いのが実情です。親知らずの抜歯には、大がかりなケースもあり、時には全身麻酔下で抜歯を行うケースも存在します。そのような場合、抜歯するために周囲を切開することもあります。
このページでは、親知らずを抜歯した際、縫うケース、縫わないケースでは、どのように異なるのかについて説明します。
なぜ、親知らずの抜歯時に切開が必要になる場合があるのでしょうか?

親知らずの抜歯では、歯肉を切開して抜いていくケースと、切開しないで抜いていくケースとがありますが、どのような時に歯肉を切開していくかを説明していきたいと思います。
抜歯時に親知らずが外側から見えないケース
まずは、親知らずが完全に顎の骨の中に埋まっていて、外側からは全く見えないケースです。この場合、歯肉を切開して開かない限り親知らずが見えてこないので、当然切開が必要になります。
抜歯時に親知らずが斜めに生えているケースは切開後に縫う必要性が
親知らずは、横や斜めに生えているケースが多いです。このケースでは、親知らずをそのまま抜こうとしても、隣の歯にぶつかってしまうため、うまく抜歯することは、ほとんどできません。そのため、親知らずをバーなどで半分に切断して、分割した後に抜いていくことになります。
その際、親知らずの半分は歯肉の中に埋まっていますので、やはり歯肉を切開してから、治療を進めていくことになります。この場合には、治療後に縫い合わせることが必要になります。
抜歯時に親知らずが中途半端に生えているケース
親知らずは正常な方向に向かって生えているが、完全に生えきっていないで、歯の頭の一部分しか見えていないケースがあります。このケースでは、治療器具で親知らずをきちんと掴むことが難しいことがあります。切開は患者様の負担が大きいため、出来るだけつかむように心がけますが、どうしても掴めない場合は、歯肉を切開して開く必要がでてきます。
この場合には、治療後に縫い合わせることが必要になります。
親知らず抜歯時に縫合を行う人と行わない人の違いは何でしょうか?
まず、基本的に歯肉を切開するケースは、傷の治りを早めるためと、止血効果を高めるために切開部分は縫合(縫い合わせます)します。
現在は10日間位で自然に吸収されてくる縫合糸もありますが、親知らずの抜歯の際には、ほぼ従来の非吸収性の糸が使用され、抜糸は、傷が治ってくる10日から2週間後くらいに行います。しかし、歯肉を切開せず、親知らずを抜歯できたケースでも縫うケースもあります。以下に親知らずの縫う、縫わないに関してケースごとに説明します。
抜歯後の穴が大きいケース
抜歯後の穴は、言わば傷口ですので、その穴が大きければ、食べカスや細菌が入り込む可能性が高くなります。食べカスや細菌が入ることによる炎症や感染を防ぐため、抜歯後の穴を縫い合わせて塞ぐことがあります。
上顎洞と抜歯した穴がつながっているケース
上顎の親知らずは、時々上顎洞と呼ばれる鼻の横にある大きな空洞につながっている事があり、抜歯をしたことで、この大きな空洞と抜歯をした後の穴がつながることがあります。この場合、上顎洞に食べカスや細菌が侵入することによる炎症や感染を防ぐため、抜歯後の穴を縫い合わせて塞ぐことがあります。
ドライソケットによるケース
下顎の親知らずの抜歯後に、ドライソケットという抜歯後の穴が2週間くらい経っても塞がらずに、顎の骨が口腔内に露出した状態になることが度々起こります。ドライソケットは、抜いた後の穴に血液がうまく集まらないのが原因で起こります。
喫煙されている患者様や、歯科治療時の出血が通常よりも少ない傾向にある患者様でドライソケットが起こりやすいです。ドライソケットが起こりやすい患者様に対しては、事前防止のため、抜歯部位の周りの骨をわざとひっかけ、出血をうながし抜歯をした穴に血液がたまるようにすることがあります。
その際に、縫合して抜いた後の穴を塞ぐか小さくしていきます。
インプラントによるケース(抜歯後のインプラント)
近年、インプラント治療がめざましく普及してきています。インプラント治療でインプラントを顎の骨の中に埋めるには、ある程度の量の骨が必要なのですが、抜歯をした所の顎の骨はそのままにしておくと、抜歯後急速に吸収されてしまうのです。この顎の骨の吸収を防ぐために、抜歯をした後に十分な消炎処置を行い、穴の中に骨再生を促す補填材を入れ、その上を特殊な膜でカバーすることがあります。
この治療法は「ソケットプリザベーション」と呼ばれる治療法ですが、この際も最終的に縫合を必要とします。ちなみに、この治療法はインプラント以外でも、前歯の抜歯を行った後にブリッジをいれるような症例でも行うことがあります。
それは、歯肉の高さが骨吸収によって不揃いになると、審美面で具合が悪いからです。
親知らず抜歯時に縫い合わせが必要なケースでも縫わないケースがある

親知らずの抜歯で、本来縫合が必要なケースでも、あえて縫わないことを選択するケースもあります。例えば、抜歯をした後の穴は大きいが、患者さんの口を開けられる量が小さいケース、嘔吐反射が強く、縫合するのが困難な患者様のケースなどが挙げられます。縫い合わせる・しないの判断は、患者様の負担と、縫うことによるメリット・デメリットをとのバランスを考え、総合的に判断します。
まとめ
親知らずの抜歯で、縫合が必要なケースを中心に述べてきました。逆に、縫合をしないケースは、抜歯した穴が小さいケース、傷の治りが早い患者様のケースなどが挙げられます。歯肉の細胞の交換サイクルはとても早く、約1週間程度と言われています。
言い換えますと、歯肉は傷口の治りが皮膚などに比べて早く、放っておいてもある程度の範囲内なら自然に再生していきます。


コメント