インプラントメニュー
| 当院の治療の特徴 | メリット・デメリット | 失敗・リスク |
| 注意事項 | 寿命 | 種類 |
| セカンドオピニオン |
インプラントのリスク
風邪で薬を飲む場合や、盲腸の手術にもリスクが伴うように、インプラント治療にもリスクは存在します。私たちは、まず患者様にご自身の治療についてしっかりと理解していただくことが最も大切だと考えています。当院では、患者様一人ひとりのリスクを丁寧に分析し、そのリスクを最小限に抑えるための対策を講じています。安全で安心な治療を提供できるよう、日々取り組んでいます。
インプラント治療のリスクと安全対策について
インプラント治療には、下記のようなリスクが考えられます。
【主なリスク】
- 手術中:隣接する歯や骨を傷つける、血管・神経の損傷、上顎洞への影響など
- 手術後:治療部位の感染、不適切な噛み合わせ、歯周組織の炎症など
これらのリスクはありますが、当院では事前の精密検査を徹底し、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を立てることで、リスクを最小限に抑えています。特に、当院ではインプラントシミュレーションシステムやCTやレントゲンによる詳細なデータ分析を基に診断を行います。医療行為に100%の安全はありませんが、私たちは日々実績を積み重ね、安心・安全な治療を提供できるよう努めています。まずは、不安なことや疑問点をご相談ください。
インプラント治療が難しい方

歯を失った時にインプラント治療は、最適な選択肢になるのは間違いありませんが、すべての方に適応できるわけではありません。ここではインプラント治療が難しいケースをご紹介します。
インプラントと全身疾患の関係について
インプラント治療は、歯を失った部分の噛み合わせを回復させる有効な手段ですが、外科的な手術を伴うため、患者の全身疾患の状態は非常に重要です。
糖尿病や心臓病、骨粗しょう症などの慢性疾患をお持ちの場合、体の治癒力や免疫力が低下していると、手術後の感染や創傷治癒の遅延が起こりやすくなります。
例えば、糖尿病の患者は高血糖の状態が続くと白血球の機能が低下し、傷口に細菌が侵入すると排除しにくくなります。また、心臓病の場合、血液をサラサラにする抗血栓薬を服用していると、手術時の止血が難しくなることもあります。骨粗しょう症では、骨の新陳代謝が低下し、インプラントと骨がしっかり結合する「オッセオインテグレーション」が妨げられる可能性があります。
当院では、患者の基礎疾患や内服薬の状況を詳しく確認し、必要に応じて内科医や専門医と連携しながら治療の可否を慎重に判断します。全身の健康状態が整っていないまま無理にインプラント治療を進めることは、インプラントの脱落や再手術につながるリスクがあるため、患者への負担が大きくなります。だからこそ、丁寧な事前評価が欠かせません。
歯周病でインプラントできないケース

歯周病は、日本人の成人の約8割が罹患していると言われるほど、身近な病気です。歯周病が進行すると、歯を支えている歯茎や歯槽骨(歯を支える顎の骨)が徐々に破壊され、最終的には歯が抜けてしまいます。歯を失った原因が歯周病の場合、インプラントを支える土台の骨も同様にダメージを受けている可能性が高く、十分な骨量が確保できないと、埋入したインプラント体を安定させることができません。
また、口腔内に歯周病菌が多く残っていると、インプラントを埋入しても天然歯と同じようにインプラント周囲炎を引き起こし、インプラントが抜け落ちる原因になります。
歯周病が原因で「インプラントできない」と診断された場合でも、適切な歯周病治療を徹底し、歯茎と骨の健康を回復させることで、インプラントが可能になるケースは少なくありません。歯周基本治療や外科的な歯周外科治療、骨造成などを組み合わせ、リスクを最小限に抑えながら治療を進めることが大切です。
骨粗しょう症でインプラントできないケース
骨粗しょう症は閉経後の女性に多く、加齢とともに骨密度が低下することで骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。顎の骨も例外ではなく、骨粗しょう症が進むとインプラントを埋入する部分の骨が脆弱化し、インプラントがしっかり固定されない恐れがあります。
さらに、骨粗しょう症の治療で使用されるビスホスホネート製剤(BP製剤)やデノスマブなどの抗骨吸収薬は、顎骨壊死(骨が壊死して治りにくくなる合併症)のリスクが指摘されています。特に静脈注射での高用量投与や長期服用の場合、抜歯やインプラント手術後に顎骨壊死を引き起こすケースが報告されています。
一方で、骨粗しょう症があるからといって必ず「インプラント不可」というわけではありません。骨密度を評価し、内科主治医と連携して薬剤休薬のタイミングを調整したり、骨造成術を併用したりすることで、リスクを下げて治療を行えることもあります。患者ごとの骨の状態を詳細に分析し、医学的根拠に基づいて最善の治療方法を検討いたします。
糖尿病でインプラントできないケース
糖尿病をお持ちの患者は、一般的に傷の治りが遅く、細菌感染のリスクが高まることが知られています。これは、慢性的に高血糖の状態が続くことで毛細血管の血流が悪化し、免疫細胞の機能も低下するためです。そのため、インプラント手術後の創傷治癒が遅れ、インプラント周囲炎(インプラントを支える歯茎や骨の炎症)を引き起こす可能性が高くなります。
とくにHbA1cが8.0%以上の患者では、術後の感染リスクが高まるとする報告もあります。重度の糖尿病や、血糖値コントロールが困難な場合は、インプラント治療自体が適用外と判断されることがあります。しかし近年では、内科医との連携のもとで適切に血糖コントロールができていれば、糖尿病患者でもインプラントが可能な症例が増えています。
当院では、内科主治医と密に連携し、必要に応じて治療前に血糖値のコントロールを整える期間を設けます。患者の全身状態に合わせて、感染予防のための抗菌薬の投与計画なども慎重に検討し、インプラント治療の成功率を高めています。
心臓病でインプラントできないケース
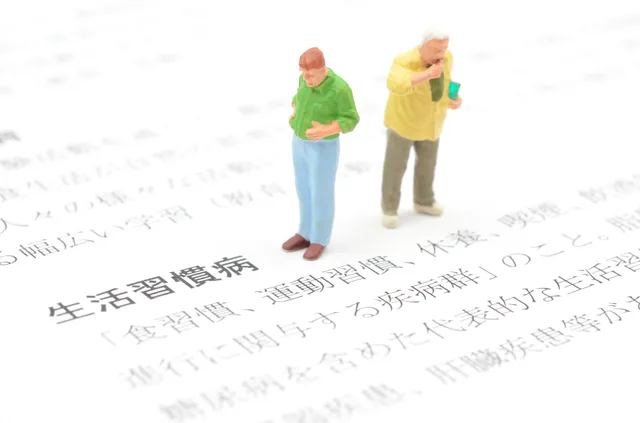
心臓病をお持ちの患者に対するインプラント治療では、心疾患そのものの影響だけでなく、使用中の薬剤にも注意が必要です。心筋梗塞や狭心症、不整脈の既往歴がある患者では、手術時のストレスや局所麻酔による循環動態への影響が心臓に負担をかける恐れがあります。
さらに、心臓病の治療では抗血小板薬(例:アスピリン、クロピドグレル)や抗凝固薬(例:ワルファリン、DOAC)を服用されている方も多く、止血が難しくなる可能性があります。抗血栓薬を無断で中止すると脳梗塞や心筋梗塞の再発リスクが高まるため、勝手に中止することは厳禁です。
そのため、当院では必ず循環器内科の主治医と連絡を取り、抗血栓療法の調整が必要かどうかを判断しながら、患者にとって最も安全な方法で治療を進めます。心臓病だからといって必ずしもインプラントが不可になるわけではありませんが、術前・術中の管理には万全の準備が不可欠です。
がん治療中でインプラントできないケース
がん治療を受けている患者の場合、抗がん剤治療や放射線療法の影響で免疫力が低下しており、手術後の感染リスクが高い状態にあります。抗がん剤は骨髄の造血機能を抑制し、白血球や血小板が減少するため、出血や感染症が重篤化しやすくなります。
特に頭頸部に放射線治療を受けた患者は注意が必要です。放射線が顎の骨に当たると骨の血流が低下し、放射線性骨壊死(顎骨壊死)という重篤な合併症を引き起こす可能性があります。放射線の線量が50Gyを超える場合は、インプラント埋入部位の骨の血行が著しく低下している可能性があり、治療の適用外とされることが多いです。
一方で、がん治療が終了して一定期間が経過し、白血球数や血小板数などの血液データが安定していれば、医科と連携の上でインプラント治療が可能となるケースもあります。治療歴や現在の体調、使用中の薬剤などを詳しくお伝えいただくことで、安全性を確保した治療計画を立てることができます。
インプラント治療を失敗しないために
一度インプラント治療が失敗してしまうと、その部位の顎の骨が吸収してさらに痩せてしまうことがあります。これは、インプラントが抜け落ちた後に骨が再生する力が十分でないためです。特に、インプラント周囲炎が原因で失敗した場合、炎症が骨の内部まで進行していることが多く、感染源をしっかり取り除かないと再治療しても同じ結果になるリスクがあります。
また、一度埋入した部位には瘢痕組織(傷あととなる線維性の組織)が形成されるため、新たなインプラントが骨と結合する「オッセオインテグレーション」が妨げられることも考えられます。このため、失敗したケースの再治療では、単純な再埋入ではなく、骨造成(GBR)やサイナスリフトなどの骨再生療法を組み合わせて骨の量と質を改善することが重要です。
当院では、失敗の原因を明確にするためにCT撮影などの精密検査を行い、炎症の有無や骨の状態を詳細に把握した上で治療計画を立てます。過去の治療歴、インプラントの材質、当時の治療法などをお聞かせいただくことで、再治療の可否や必要な処置の選択肢が広がります。
喫煙がやめられないケース

喫煙はインプラント治療において、最も大きなリスク要因の一つです。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯茎や顎の骨への血流を阻害します。これにより、骨とインプラントが結合するオッセオインテグレーションが阻害され、治癒が進まずインプラントが脱落しやすくなります。
さらに、喫煙は唾液の分泌量を減少させ、口腔内の自浄作用を低下させます。これによりプラーク(歯垢)がたまりやすくなり、インプラント周囲炎の発症リスクが大幅に高まります。実際に、非喫煙者と比較すると、喫煙者のインプラント脱落率は2倍以上とも報告されています。
そのため、喫煙が習慣化していて禁煙が難しい方は、インプラントが「できない」「適用外」と判断されることもあります。しかし、治療成功の可能性を上げるために、禁煙外来などの医療サポートを活用し、治療前後の禁煙を徹底することを強くおすすめします。患者の治療意欲と健康への意識が成功の鍵を握っています。
骨が不足しているケース
インプラント治療では、人工歯根をしっかり固定するために十分な骨量と骨質が必要です。歯を失った部分の骨は、噛む刺激がなくなると吸収されて徐々に痩せていくため、失歯後の期間が長いほど骨量不足が起こりやすくなります。
上顎の奥歯の上方には「上顎洞(サイナス)」と呼ばれる空洞があり、歯槽骨が薄いとインプラントを埋入する際に上顎洞に穴が開いてしまうリスクがあります。この場合には、サイナスリフト(上顎洞挙上術)という特殊な骨造成手術を行い、人工骨などを移植して骨の高さを確保します。
また、前歯部分など骨の幅が狭いケースではGBR(骨誘導再生療法)を行い、骨の幅を増やしてからインプラントを計画することがあります。これらの骨造成術を適切に併用することで、多くの骨不足のケースでも治療が可能になります。ただし、骨造成には術後の腫れや治癒期間の延長などのリスクも伴うため、詳細な診断と丁寧な治療計画が不可欠です。
インプラント治療が不可・適用外といわれた方へ
医師から「インプラントはできない」「適用外」と言われたとしても、すべてのケースで可能性が完全にゼロになるわけではありません。全身疾患であれば内科主治医と連携して病状を安定させることで、インプラント治療が可能になる場合も多くあります。また、骨量不足も高度な骨造成技術で解決できることが増えています。
それでも、どうしても全身状態や局所の条件から安全にインプラントができない場合は、患者の噛み合わせや残存歯の状態に合わせて、入れ歯やブリッジといった他の補綴治療を提案します。最近ではインプラント以外の治療法でも機能性や審美性を高める方法が進歩しています。
大切なのは、患者一人ひとりにとって最善の選択肢を一緒に考えることです。「インプラント治療は不可」と諦める前に、ハーツデンタルクリニック八千代中央駅にご相談ください。
