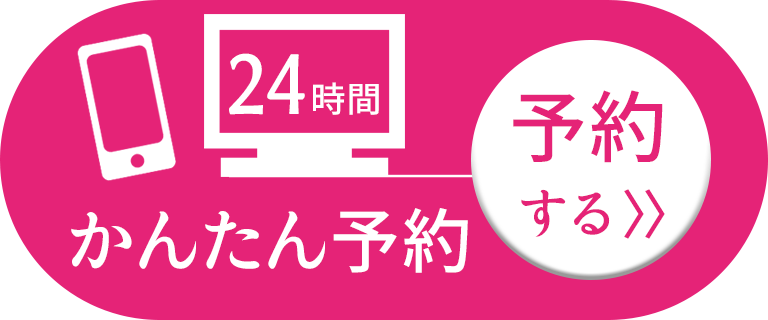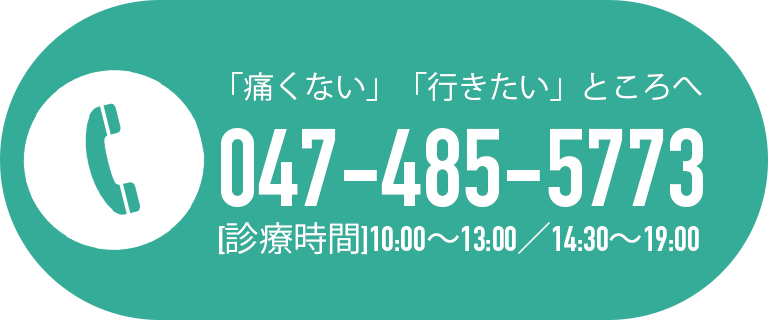当院における静脈内鎮静法の特徴
当院では静脈内鎮静法は「保険適応」で行っております。
保険でできる静脈内鎮静法を施行するには、付帯条項として、全身麻酔症例200症例以上かつ鎮静法症例20例以上の経験を有することが望ましいとなっています。
これは歯科麻酔学会が認定医試験を受験する条件となっていることが根拠にあると思われます。
さらに専門医に取得するには、ハードルは高くなり、大学の歯科麻酔科に属さないかぎり、不可能です。
院長の高田は30年間大学の歯科麻酔科に属しており、認定医かつ専門医を有しており、現在、鎮静症例数は1万以上の症例数を経験しております。
静脈内鎮静(無痛治療)のご紹介
静脈内鎮静法(点滴麻酔)により、難しい抜歯等の外科治療を半分眠っているようなウトウトとした状態で治療を受けることができます。その上、治療終了後には、そのまま帰宅可能です。日本歯科麻酔学会認定が歯科治療に強い恐怖心をお持ちの方を丁寧に治療致します。
静脈内鎮静法(無痛治療)は、こんな方にオススメ!
- 歯科医院に恐怖感があり、今まで通院できなかった…
- 「痛い」「怖い」から解放されて抜歯や外科治療を受けたい…
- 親知らずの抜歯や神経の治療だけでも眠った状態で治療してほしい…
- 小さな子供の場合、歯磨き粉を食べたり、飲み込んだりしてしまう。
- 嘔吐反射(オエッとなりやすい)が激しい…
歯科で使用する麻酔の種類
歯科治療において「痛くない治療」を実現するためには、患者様の症状や不安の程度に応じた麻酔の使い分けが重要です。ここでは、当院で対応している代表的な4つの麻酔方法をご紹介します。各麻酔の詳しい説明は後段で解説していますので、併せてご参照ください。
表面麻酔
注射の針を刺す前に歯ぐきの表面に塗布する麻酔です。ジェル状の塗る麻酔やシール状の麻酔があり、注射時のチクッとした痛みを和らげます。歯科治療に恐怖心がある方やお子様にも有効です。
局所麻酔
治療部位の神経に直接作用して痛みを遮断する基本的な麻酔です。「浸潤麻酔」は狭い範囲に作用し、むし歯治療などに使われます。一方、「伝達麻酔」は広い範囲に効果が及ぶため、親知らずの抜歯や外科処置に用いられます。
笑気麻酔
酸素と一緒に吸入することでリラックスできるガス麻酔で、軽い鎮静効果があります。不安感が強い方や、お子様にも適しています。意識はある状態で治療を受けられ、吸入をやめるとすぐに効果が切れるのが特徴です。
静脈内鎮静法
点滴で鎮静薬を投与する方法で、「ウトウト麻酔」「眠くなる麻酔」とも呼ばれます。治療中の記憶がほとんど残らないほどリラックスでき、インプラントや長時間の外科処置などに適しています。
また、入院施設のある病院では「全身麻酔」による治療も可能で、完全に眠った状態で処置を行います。小児や重度歯科恐怖症の方の全顎治療など、限られたケースで選択されます。
静脈内鎮静法(無痛治療)は痛くない
鎮静剤が効いてくると浅く麻酔がかかったようになり、難しい抜歯等の外科治療でも半分眠っているようなウトウトとした状態でほとんど痛みを感じずに受けることができます。ただし!静脈内鎮静法には健忘作用もあるため、中には治療中の記憶が残らない方もいます。
全身麻酔のほうがいいのでは?
中には「全身麻酔」で親知らずなどの治療をしたほうが良いと入れるケースもございますが、全身麻酔では、まったく意識がなくなるので完全に痛みを感じずにすみますが、そうなると自然と呼吸をしなくなるため、人工呼吸(呼吸管理)が必要となります。したがって、身体にかかる負担は大きくリスクも高くなり入院をしなくてはなりません。
それに対して、静脈内鎮静法は完全に意識がなくなるわけではないので(たまに眠ってしまう方もいますが)、リスクも低く、個人差はありますが、基本的には治療が終了したならば、すぐに帰宅することが可能です。
ハーツデンタルで静脈内鎮静法(無痛治療)の利用すべき理由
①保険適用される可能性がある
基準は明白で歯科治療恐怖症や異常絞扼反射といった病名がつけられるかどうかです。歯科治療恐怖症というのは、歯医者で治療を受ける際に、恐怖心や不安が高まってしまう病態で、れっきとした病気として捉えられています。こうした病気のある患者さんは、通常の虫歯治療はもちろんのこと、歯茎の切開や骨の切除などを伴う親知らずの抜歯、それからインプラント手術などを受ける際には、大きな危険が予想されます。
もしも処置中に恐怖で頭が混乱したり、異常絞扼反射で激しい嘔吐反射が起こったりした場合は、口腔内を傷つけてしまう事態も考えられるのです。そうした医療事故を防ぐためにも、静脈内鎮静法が必要になります。
②保険適用で料金が安い
静脈内鎮静法(無痛治療)は、保険が適用されると治療費+2500円~3000円程度の出費ですみます。
一度、試してみてください
今まで述べてきたように、歯科医院における静脈内鎮静法は、歯科治療に恐怖心がある方や物が口の中に入るとおぇっとする方、高血圧症や糖尿病といった基礎疾患を有する方にとって、さまざまな利点がある方法です。
静脈内鎮静法は、体制や設備が整っていれば、安全性の高い鎮静法ですので、ぜひ、お気軽にご相談ください。
費用(保険適用)
処置代+2,400~3,000円
静脈内鎮静法の流れ
無痛治療・痛くない治療を可能にする静脈内鎮静法は、次のような流れで進行します。
STEP1 体調の確認
ご来院いただきましたら、まずは体調のチェックを行います。気分が悪い、手術が心配など、どんなことでも構いませんので、不安に思う点があればお伝えください。大掛かりな歯科治療や外科手術は、心身ともに万全の状態で受けることが大切です。当日の体調に問題がなければ、静脈内鎮静法や手術の注意事項をお伝えします。
STEP2 生体監視モニターの装着
静脈内鎮静法では、全身状態の管理を徹底します。その上でモニタリングが必要なのが血圧や呼吸数、心拍数などです。手術中に痛みを感じたり、強い不安感に襲われたりすると、血圧や呼吸数に変化が現れます。そうした体調の変化が見逃さないためにも、生体監視モニターが必要となるのです。具体的には、血圧計やパルスオキシメーターなどを装着します。パルスオキシメーターは、指の先に挟むだけで動脈中の酸素濃度を測定できる装置です。
STEP3 静脈路の確保
鎮静剤を投与するための静脈路を確保します。腕に注射針を刺して、点滴を打てる状態を作ります。
STEP4 鎮静剤の投与
静脈路が確保できたら、鎮静剤を投与します。鎮静剤の投与量は患者さんの体重や体調などを考慮した上で厳密にコントロールします。薬液を投与してからしばらくすると気持ちが軽くなり、半分眠ったような状態へと移行します。全身麻酔のような意識を完全に失う状態とはことなり、スタッフと会話することが可能です。手術中でも何か不安なことがあれば、歯科医師や歯科衛生士にお伝えください。
STEP5 歯科治療・外科手術の開始
鎮静剤の効果が確認できたら手術の開始です。痛みは局所麻酔で、不安感や恐怖心は鎮静剤で抑えられているため、リラックスした状態で無痛治療を受けられます。手術中は、麻酔担当の歯科医師が患者さんの全身状態をモニタリングしているので、異常が生じた際には迅速に対処できます。
STEP6 治療終了・リカバリー
歯科治療・外科手術が終わったら、鎮静剤の投与を停止します。静脈内鎮静法で用いる薬剤は、投与を停止した後もしばらく効果が継続するため、元の状態に戻るまでは休憩室で休んでいただくことになります。リカバリーには2~3時間程度かかります。歯科医師を始めとしたスタッフが眠気やふらつきがないことを確認したら、注意事項をお伝えした上で帰宅していただきます。
静脈内鎮静法のデメリット
静脈内鎮静法は、無痛治療・痛くない治療を実現できる優れた麻酔法ではありますが、いくつかのデメリットを伴います。
◎鎮静剤による副作用、リスク
ご静脈内鎮静法のデメリットとしては、鎮静剤に伴う副作用・リスクが第一に挙げられます。具体的には、「プロポフォール」で血管浮腫や低血圧を伴うアナフィラキシーショック、「ミダゾラム」では呼吸抑制や無呼吸、舌根沈下などのリスクを伴います。これらはあくまでリスクであり、歯科麻酔の専門家が立ち会うことでその可能性を限りなくゼロに近付けることができます。
◎治療時間が長くなる
無痛治療・痛くない治療で行われる静脈内鎮静法は、笑気麻酔とは異なり、リカバリーまでに相応の時間がかかります。手術前に静脈内鎮静法を実施する時間も必要となることから、治療時間が長くなるというデメリットを伴います。
◎追加費用がかかる
静脈内鎮静法をオプションとして選択した場合は、追加で費用がかかることになります。保険が適用されれば2,500~3,000円程度、自費診療の場合は数万円の費用が加算されます。
◎十分な設備と適切な人材が必要
静脈内鎮静法を安全に遂行するためには、十分な設備と適切な人材が必要となります。とくに静脈内鎮静法の実績豊富な歯科麻酔医の確保が何より重要となるため、どの歯科医院でも同等の無痛治療が受けられるということにはなりません。
静脈内鎮静法を受けられない人
次に挙げる人は、静脈内鎮静法を受けることができません。
- 妊娠している人
- 口が大きく開かない人(呼吸管理が難しいため)
- 持病により全身状態が安定しない人
- 使用する鎮静剤に対する禁忌症やアレルギーを持っている人
その他にも静脈内鎮静法を適応できないケースはありますので、服用中のお薬や治療中の病気、過去の既往歴などは事前に申告していただくことになります。無痛治療・痛くない治療を安全に実施すためにもご協力をお願い致します。
静脈内鎮静法がウトウト麻酔・眠くなる麻酔と呼ばれる理由
「静脈内鎮静法」は、点滴によって鎮静薬を体内に直接投与する麻酔方法で、「ウトウト麻酔」や「眠くなる麻酔」とも呼ばれています。この方法は、歯科治療への強い不安感や恐怖心がある方に特に適しており、全身麻酔とは異なり意識はうっすらあるものの、治療中の出来事をほとんど覚えていないほど深いリラックス状態を得られるのが特徴です。
この麻酔法が選ばれる最大の理由は、“痛みへの感覚が鈍くなる”だけでなく、“治療に対する心理的ストレスも軽減できる”ことです。歯の治療音や振動に敏感な方、嘔吐反射が強い方、長時間の処置が必要な方などにも適応されることが多く、患者様は「怖くなかった」「気づいたら終わっていた」と感想を述べられます。
また、静脈内鎮静法は麻酔科や歯科麻酔を専門とする歯科医師の管理のもとで行われ、安全性にも十分配慮されています。治療中は心拍や血圧、酸素飽和度などがモニターで常時管理されるため、持病のある方でも安心して治療に臨むことができます。点滴麻酔による「眠くなる麻酔」は、まさに“ストレスフリー歯科”や“リラックス歯科”の象徴的存在といえるでしょう。
痛くない歯医者・怖くない歯医者が選ばれる理由
多くの患者様が「痛みが怖い」「麻酔の注射が苦手」「治療の音が不快」といった理由で歯科受診を避けてしまう傾向にあります。そうした背景から、近年では「痛くない歯医者」「怖くない歯医者」というキーワードで医院を探す方が増えており、歯科医院側も“痛みの少ない治療”を重視する傾向にあります。
特に現代の歯科医療では、技術の進歩により“痛みを最小限に抑える工夫”が数多く導入されています。具体的には、表面麻酔の併用、細い注射針、電動麻酔器の使用、刺入速度の調整などが挙げられます。また、患者様との丁寧なコミュニケーションも欠かせません。不安を抱えたまま治療に臨むのではなく、治療の流れや麻酔の種類について事前にしっかりと説明を受けることで、心理的な安心感につながります。
こうした配慮が行き届いた医院では、歯科治療に対する恐怖感が払拭され、定期的な通院に前向きな気持ちで通う方が増えています。痛くない・怖くないというイメージは、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療にもつながり、結果として患者様の健康維持にも大きく貢献しています。“ストレスフリー歯科”や“リラックス歯科”が選ばれる理由は、こうした患者様の安心感と信頼の積み重ねにあるといえるでしょう。
手術当日の注意点
静脈内鎮静法を伴う手術当日には、以下にご注意ください。
◎来院方法について
ご自身の運転する自動車での来院は原則として禁止させていただきます。リカバリーした後もしばらくは鎮静剤の効果が残り続けるため、付き添いの方が運転する自動車か公共交通機関を使って帰宅していただくことになります。
◎手術前の食事について
手術当日の食事は、静脈内鎮静法を実施する3時間前には食事を済ませておいてください。鎮静時に嘔吐すると、気道を閉塞したり、誤嚥して肺炎を引き起こしたりするリスクがあるため、軽めの食事にとどめると良いでしょう。水による水分補給も施術の1時間前からは控えるようにしてください。
◎手術後の行動について
手術が終わって帰宅した後は、激しい運動や飲酒、熱い湯船に浸かることなどは避けてください。これらは血流を良くすることで傷口を開くとともに、全身状態も不安定にさせます。
表面麻酔について
歯科治療に対する不安や痛みへの恐怖を軽減するために、近年では「表面麻酔」が広く活用されています。表面麻酔は、針を刺す前に歯茎や粘膜の表面に麻酔薬を塗布することで、注射時のチクッとした痛みを和らげる処置です。
「塗る麻酔」や「シール麻酔」といった名称で呼ばれることもあり、患者様の緊張感を軽減する効果があります。
表面麻酔の種類
表面麻酔には大きく分けて2つの種類があります。ひとつはジェルタイプで、綿棒などを使って直接歯茎に塗布します。もうひとつはパッチタイプの「シール麻酔」で、必要な部位に一定時間貼り付けて作用させる方法です。どちらも表層の知覚神経に麻酔が作用し、注射時の痛みを感じにくくする効果があります。
こうした前処置を丁寧に行うことで、注射そのものが「いつ刺されたかわからなかった」と驚かれる患者様も少なくありません。特にお子様や歯科恐怖症の方、過去に痛い経験をされた方にとって、表面麻酔は“痛くない歯医者”を実現するために欠かせない工程となっています。
歯科麻酔の認定医・専門医について
無痛治療をより安全に、そして確実に提供するには、歯科麻酔の専門知識を持つ医師の存在が欠かせません。「歯科麻酔認定医」や「歯科麻酔専門医」は、日本歯科麻酔学会の定める研修と試験を経て認定される資格で、口腔外科手術や静脈内鎮静法、全身管理を必要とする治療を安全に遂行する知識と技術を有しています。
こうした麻酔の専門資格を持つ歯科医師は、患者様の全身状態を見極めたうえで適切な麻酔方法を選択し、副作用や合併症のリスクを最小限に抑えることができます。特に高血圧や糖尿病などの持病をお持ちの方、高齢の方にとっては、全身の健康状態を総合的に考慮した麻酔管理が重要になります。
また、歯科麻酔の認定医が常駐する医院では、万が一の異常に対しても迅速かつ適切な対応が可能であり、患者様の不安解消にもつながります。静脈内鎮静法などの“点滴麻酔”を安心して受けたいと考える方は、麻酔の専門医が在籍しているかどうかを一つの判断材料にされるとよいでしょう。
“痛くない歯医者”を支えるのは、医療機器や麻酔薬だけではなく、それらを扱う歯科医師の技術力と判断力です。ハーツデンタルクリニックでは、歯科麻酔に関する知識と経験をもとに、すべての患者様がリラックスして治療に臨めるようサポートしています。
ハーツデンタルクリニック八千代中央駅前(歯科医院)

| 院長 | 歯科医師 歯学博士 高田耕司(たかだ こうじ) |
|---|---|
| 経歴 | 昭和61年東京医科歯科大学歯学部歯科麻酔学教室 医員 平成1年日本大学助手歯学部歯科麻酔勤務 平成4年日本大学講師歯学部歯科麻酔勤務 平成5年ロンドン大学精神医学研究所留学 平成15年日本大学専任講師 平成28年日本大学歯学部退職 埼玉県社会福祉事業団 嵐山郷歯科室 非常勤 よしだ歯科院 勤務 平成29年エバト歯科院 勤務 令和1年ハーツデンタルクリニック 勤務 所属学会 日本歯科麻酔学会、日本障害者歯科学会 取得資格 昭和63年8月)日本歯科麻酔学会認定医(第383号) 平成4年11月歯学博士(第4540号) 平成6年10月日本歯科麻酔学会専門医(第81) 専門分野 歯科治療時における全身管理 |